私の活動は展示会等の開催による広報活動、セミナー・ワークショップによる教育訓練、経営、生産、品質、新製品開発、市場調査、営業戦略、広告等に対し情報提供、助言を行うことです。そしてこれらを通じて、ラオスの伝統文化の維持、及び会員の利益や競争力向上を図ることです。
私のラオスに対する感想は、「自助努力よりも援助に頼る」考え方が主流であること、情報等を提供しても、それを上手く利用して商売に結び付けようといった考え方が乏しく、非常に残念なことです。私はその辺りをカバーすべく、微力ながらラオスの発展に貢献したいと思っています。
青年海外協力隊 松 田
(ウドムサイ県フン郡病院、看護師)
私がラオスに赴任してもうすぐ2年が経過します。日々の活動のなかで、日課としていることがあります。それは毎朝、患者様のベッドサイドへ訪問し、お話することです。私の活動拠点は郡病院ですので、もし、長期にわたり入院の必要性があって、お金がある患者様は県病院へ転院されていきます。そしてお金のない患者様は「祈祷師にお祈りをしてもらう」といって自宅に戻られます。
診断・治療のための医療器材のそろわない郡病院でできることは限られています。それでも、もう少し様子を見たい、輸血さえすれば…とういうケースもあります。しかし「お金がない」という理由で治療の継続を拒否されると私にはどうしようもありません。「お金がない」という状況を改善することは、私にはできません。この状況で私にできることは患者様自身の生命力の強さと、祈祷師のお祈りの効果があることを祈るのみです。
適切な医療・看護を提供することもできず、亡くなっていく患者様をみていると「自分は何をしにここまで来たのか…」と無力感でいっぱいになります。現在の私の活動が、いまの地域住民に還元されるものではなく、数年後この病院の看護スタッフの知識・技術レベルが向上してきてはじめて私の今の活動が意味を持つのだと思います。そういう日がきっとくると信じて毎日活動しています。
青年海外協力隊 鶴 田
(サバナケット県保健学校、看護師)
みなさんこんにちは。私はJOCVとしてサワンナケート県保健学校に派遣されている鶴田と申します。6月末で、保健学校に配属となりちょうど1年。この1年間は、日本で看護師として働いていた実績を生かすこともできず、言葉の壁、文化の違い、価値観の違いに悩み戸惑ったあげく、ここでの自分がいる意味を問い続けた年だったように感じます。そんな私もやっと最近になって『ボーペンニャン』精神が育ってきたのか、少しづつ楽しみも増えてきました。
 保健学校では、日本から提供された機材が多くありますので、それを使用しながら看護技術の演習をラオ人の先生と一緒に指導したり、学校の中でさえも、行事が終った後は『キンリアン』。そう、ラオ人の大好きな宴会にも参加して、先生や学生と共にお酒を飲んだり踊ったりしています。写真は今年のピーマイのときに学生達と撮った写真です。バーシーをしてお互いの幸せをたくさん祈り、祈らせていただきました。JOCVとしての活動も折り返し地点の今、一日一日を大切にして過ごしていきたいと思っている今日この頃です。
保健学校では、日本から提供された機材が多くありますので、それを使用しながら看護技術の演習をラオ人の先生と一緒に指導したり、学校の中でさえも、行事が終った後は『キンリアン』。そう、ラオ人の大好きな宴会にも参加して、先生や学生と共にお酒を飲んだり踊ったりしています。写真は今年のピーマイのときに学生達と撮った写真です。バーシーをしてお互いの幸せをたくさん祈り、祈らせていただきました。JOCVとしての活動も折り返し地点の今、一日一日を大切にして過ごしていきたいと思っている今日この頃です。
|
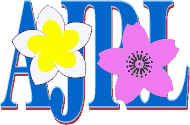


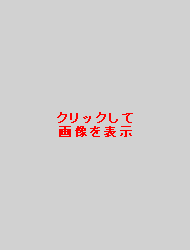 (ハンディクラフト協会、繊維マーケティング)
(ハンディクラフト協会、繊維マーケティング)